〈俳優〉と〈ライター〉は似ている。どちらも監督(編集者)の構築しようとする世界を実現するために、みずからのスキルを最大限使って表現する者だ。
となると、“役者魂”からライターの極意を学べるかもしれない——そんな仮説を立ててみた。
ここに『「お葬式」日記』『「マルサの女」日記』『「大病人」日記』(いずれも文藝春秋刊)という3冊の本がある。映画監督・伊丹十三氏が映画づくりについて書いたものだ。伊丹氏自身も俳優だから、演出する側・される側両方の視点から創作論が綴られている。
今回は伊丹十三監督の創作論からライターの心得を探ってみよう。
この記事の内容
“俳優”の5つの大罪はライターの罪
伊丹氏は『「大病人」日記』において「俳優の5つの大罪」を語っている。これを反面教師にして「プロのライターとして守るべき最低ライン」を見極めることにする。
1.〈セリフのウロ覚え〉は記事のレベルを下げる
伊丹氏が一つ目の「大罪」として挙げているのが「セリフのウロ覚え」だ。
僕の場合は俳優さんにセリフをテニヲハまできっちり正確に覚えてもらって、句読点以外のところでは切らないでどんなスピードでもいえるようにして現場に来てもらう、というのが原則ですから
『「大病人」日記』
セリフがウロ覚えだと、セリフをきちんと言えなかったりトチったりする。セリフをちゃんと言えるようになるまで、まわりの人は手を止めなければならない。これは「大変レベルの低い仕事でしょ」と、伊丹氏は言う。
俳優の「セリフのウロ覚え」は、ライターにとってどんな〈罪〉にあたるか。それは〈コトバ〉や〈文章〉を自由に操れない、もしくはそれに難儀して時間がかかってしまう、ということになると思う。
どんなジャンル、どのようなテイストの記事であれ、最低限読み物として成立させることができる。それは、適切な文体であったり、正しい単語の選択であったり、的確な論理展開であったり。記事にふさわしい表現力を使える、ということだ。
その最低ラインをクリアしてこそ、監督(編集者)は記事の質を底上げできる。監督が演出することは、さしずめ編集者が原稿に赤を入れることと同じ。編集者が赤入れするのは及第点を取るためではなく、クォリティをアップさせるためだ。それこそがプロの現場というものだろう。
2.〈遅刻〉は記事の質を損なう
二つ目の〈大罪〉は「遅刻」。
遅刻と限らずわがままはいけません
『「大病人」日記』
俳優やライターに限らず、仕事をする者として〈遅刻〉しないことは最低限のルールといえる。
ライターにとっての「遅刻」は、取材や打ち合わせの場に遅れることもあてはまるが、ここでは「締め切りを守らない」ことと言い換えたい。
ライターが“遅刻”をするとどうなるか。記事の制作プロセスが遅滞する。編集者のチェックも遅れるし、雑誌などの紙媒体であれば、ゲラが出るのが遅くなる。
「ライターはいったん原稿を書き上げたら、そこでお仕事終了」というケースもあるだろうが、たいていはライター自身も校正を行なうはずだ。その作業も遅れる。自分の首を絞めることになるわけだ。
「結果的に、本の発売や記事の公開に間に合えばいいじゃないか」と考える人も、もしかしたらいるかもしれない。だが、制作プロセスの遅れは、記事の質に大きく関わってくる。ライティング作業の重要度は、制作プロセスの全体から見れば2〜3割程度のもの。ライターが原稿を書き上げてから、いかに“直す”かが勝負なのだ。
そう考えると、俳優よりライターの“遅刻”のほうが罪深いといえるかもしれない。
3.〈ホンが読めない〉と記事は迷走する
俳優は台本を受け取ったら、まずは白紙の状態でストーリーを読む。次に自分の役で読んでいく。役がつかめたら個々のシーンの検討を始める。ところが、悪い俳優は自分本位で読み始めてしまう。
ストーリー全体から見てそのシーンを意味づけることができない。
『「大病人」日記』
台本に書かれたセリフは、ストーリー上の意味を持っている。そこを読み取らなければならないが、悪い俳優はそれができない。
悪い俳優はただ思いつきだけ(笑)自分が目立てればそれでいい。
『「大病人」日記』
では、ライターにとってホン(台本)が読めない、とはどういうことか?
それは、メディアにおける記事の意味づけを理解しない、ということになるだろう。
どんなメディアあれ、ライターが取り組もうとしている記事は、なんらかの目的を実現するために制作される。読み手に有益なノウハウを紹介することだったり、会社のブランディングを担うものであったり。目的をふまえなければ、記事の内容は明後日の方向にいってしまう。“ホン”が読めていれば、記事に盛り込むべき情報や展開のしかたはおのずと決まってくるはずだ。
ただ、俳優とは異なり、ライターに“ホン”が渡されるケースは少ない。もちろん、企画書という名の“ホン”がつくられることもあるが、そうでない場合はどうするか?
目に見えるカタチで“ホン”が存在しなくても、編集者(発注者)の頭の中にはあるはずだ。だから、それを“見せて”もらう。編集者に徹底的にヒヤリングして、お互いに記事の完成イメージを共有する。俳優が手にするホンも、そもそもは監督や脚本家の頭にあるイメージを制作陣で共有するためにつくられるものだ。
編集者の頭に“ホン”が存在しなかったり、編集者自身がメディアにおける記事の意味づけを理解していなかったりするケースもある。その場合は、ライター自身が“ホン”をつくる、すなわち編集者の代わりに記事の“世界”を創るしかない。むしろ、今後はそこまで踏み込めるライターになって、みずからの価値を高めていくべきかもしれない。
4.〈位置に入らない〉と記事は成り立たない
映画は機械仕掛けで撮られる。簡単にいえば、俳優はカメラのピントが合う位置で芝居をしなければならない。
どんないい芝居をされても、それを撮る段取りが機械側にできていなきゃ、撮りたくても撮れないし、撮っても写りません。
『「大病人」日記』
悪い俳優は、何回やっても動きが定まらずピントがぼけてしまう。「位置を合わせる」ことは、俳優のイロハのイというわけだ。
これをライターに敷延するとどうなるか?
雑誌のライターであれば、「レイアウトの文字数に合わせて文章を書く」ことに相当するだろう。1行でもハミ出せば、あきらかに不体裁になるのだから、必須の技術だ。
とはいえ、これは雑誌を制作する場合、それも先割り(原稿ではなくレイアウトを先につくる)の場合に限るだろう。1文字単位で文字量を調整するのは、ライターの仕事のなかでも特殊かもしれない。
ただ、どんなライターであっても、メディアの求めるボリュームに文章量を合わせることは必要になる。書籍であれば、(よほどの大作家でない限り)価格や折の関係でページ数はあらかじめ決まってくる。それにともない各章やセクションのページ数も確定する。容れモノに合わせて原稿を制作しなければならないのだ。
スペースの制限がないと思われがちのウェブメディアも、紙メディアより制約は緩いものの、記事の内容によって必要とされるボリュームを見極めなければならない。なぜなら、ムダに長い記事はユーザーが読むのを止めてしまうからだ。
やはりどのようなライターであれ、“位置”に入ることは身につけるべきスキルといえるのだ。
5.〈協調性のない俳優〉の仕事はしぼんでいく
俳優の5つの大罪として、伊丹氏は最後に〈協調性のない俳優〉を挙げる。
コミュニケイションの悪い人、自分の殻に閉じこもってしまう人、こういう人はとかく役の作りが自分本位で自閉的になりやすい。肝腎のところで相手を見ない。相手のいうことに反応しない。
『「大病人」日記』
ここでいう「相手」とは共演している人のこと。「殻に閉じこもってしまう」「自閉的」「相手を見ない」とは、芝居のうえでのことだろう。
俳優にとっての「芝居」は、ライターの「記事づくり」そのものといえる。「相手」は編集者。「記事づくり」のうえで「殻にとじこも」ったり、「自閉的」であったりしてはならない。編集者との「協調性」や「コミュニケーション」は、良質な記事づくりには欠かせない要素だ。
編集者は仕事の発注者だから、ときにライターが卑屈になったり、逆に理不尽な要求に腹を立て反抗的になることもありえる。もちろん、これは健全な関係とはいえない。
撮るほうだって、その人の芝居撮ってもいつも一人芝居で、相手とのコミュニケイションに関しては面白いことが何も起こらないことがわかってるから、次第に撮り方が消極的になってくる。結果として役がしぼんで小さくなってしまう。長期的には、スケールのある、人間味豊かな役は、その人のところへは段段来なくなるでしょうね
『「大病人」日記』
とどのつまりは、いっしょに仕事をする相手、ビジネスパートナーと良好な関係を築くことが大切——という当たり前の真実に行き着いてしまうが、ライターもまた例外ではないことを肝に銘じておきたい。
俳優(ライター)が持つべき心得とは?
最低限 守るべき事柄をおさえたところで、よい仕事をするための心得を引き続き伊丹監督の著書からつまんでいこう。
言葉を勉強する
伊丹氏は、日本の俳優に共通する欠点として「言葉に対して不勉強」である点を挙げる。
言葉を操れない。言葉を道具のように使えない。言葉で意味を伝えることが苦手である。言葉が全部情になってしまう。情だけがハラワタのようにヨダレのように出てくるのでとても気持ちが悪い。情だけの役ならそれでいいのでしょうが、論理や意味を伝えることができない。
『「大病人」日記』
〈言葉を操る〉のが仕事という点で、俳優とライターでは大きな共通点がある。とくに「言葉が全部情になってしまう」という問題の指摘は傾聴に値する。プロのライターも「情」で文章を綴ってはならないのだ。
ライターというのは、なんらかの価値を読み手に伝えるのが本分だ。ある種のレトリックとして表面に「情」をまぶすことはあっても、書いている本人が「情」に流されてはならない。そうでないと、伝えるべき「価値」が的確に読み手に届かなくなってしまうからだ。
感動したエピソード、とても役に立った商品・サービス、心動かされた作品など、書き手が感じた「情」を伝えたいときはある。ただし、あくまで「情」を伝えるのであって、「情」で伝えるのではない。
そうならないために俳優が心がけておくべき点は、ライターにもまた有効だ。伊丹氏はこう語る。
俳優は言葉を操るのが商売ですから、言葉とは常日頃仲よくしておくことが絶対条件です。そのためには言葉を最も厳密に使っている書物、つまり理論的な書物に馴れ親しむ努力が是非とも必要だと思います。
『「大病人」日記』
単に書物に、言葉に親しむのではなく、理論的な書物・言葉に日ごろから触れておく。これは意識していないとなかなかできないことだ。
孤独に耐える
俳優にとって、さらに大切なこと。それは「孤独に耐える力」だと言う。
役を作って役の中に入ったら、無説明にそれに耐えるということが必要でしょう。
『「大病人」日記』
これは、実際には「孤独に耐える力」に乏しい俳優が多いことを意味している。
ところが日本の俳優は〈どうです? うまく見える? 僕、カッコいい?〉とたえず観客にしなだれかかってしか芝居ができない。相手がどう思うか、ウケるか、ウケないか、うまく見えるかどうか、たえず人の顔色見て芝居している。要するに自立できていない。これでは弱い弱い子供っぽい人格しか演じることができないでしょう。
『「大病人」日記』
これは意見が分かれると思うが、個人的に良い文章とは——いや自分が目指すべき文章とは「読み手に良い文章だと思わせない文章」だと考えている。文章の善し悪しを意識させないうちに最後まで読ませる。これが「良い文章」だ。
文章の善し悪しを意識させないのは、文章に「書き手」の存在が出てこないから。〈どうです? うまく見える? 僕、カッコいい?〉と主張していないからなのだ。
もちろん、書き手の個性をウリにする文章はあるだろう。それが悪い文章だともいえない。ただ、そういう文章の書き手は「ライター」というより「作家」に近い存在だろう。それは個人的に歩むべき道ではないと考える。
伊丹氏は、俳優の仕事は「死ぬこと」だと語る。
だから僕は俳優に対して、俳優は死ななきゃいかんというんです。スクリーンの中で役の人物として生きるためには俳優としては死ななきゃならん。きっちり死んだ人ほど役としてよみがえれるのだト。俳優として死んでくれるほど、観客は自分の分身や変身を彼の上に見ることができるのだト。
『「お葬式」日記』
ライターも、読み手が文章を読んでいるときは「死んでいる」ことが必要。そうでないと、文章そのもの、ひいては文章が伝えるべき「価値」そのものに目が向かない。いわば文章が生きない。
最終的に消えることのできるライター。これを目指していきたい。
より高みを目指すための指南
プロフェッショナルとして仕事をするならば、つねに試行錯誤、自己研鑽を心がけていきたい。俳優(ライター)がより高みを目指すために、なにをすべきか。これも伊丹氏の著書から探っていこう。
仕事がつまらないなら面白くする
俳優という職業には特殊な事情がある。それは「依頼されるまで仕事が発生しない」ことだ。言い換えれば、みずからが発注者になることはない。つねに受け身なのだ。
たとえば俳優というのは仕事に関していいますと、これは仕事を与えられる存在ですからね。いくらいい仕事だけ選んで仕事しようと思っていても、そもそも選ぶべき仕事が充分にない状態じゃどうにもなんない。
『「お葬式」日記』
これは、ライターにもぴったり当てはまる。編集者から依頼を受けることで初めて仕事が成立する。ライターから企画を持ち込むこともあるだろうが、依頼されなければ仕事が発生しないのは同じだ。
そうなると、「どうしていい仕事が来ないのだろう」とか「もっと自分の力を発揮できる仕事がしたい」などと欲求不満に陥ることもあるだろう。俳優と同様、受け身の仕事である以上は宿命みたいなものだ。
だが、それでいいのかと、伊丹氏は疑問を呈する。
ただね、大の男が来る日も来る日も、ああつまんない、なんでこんなにつまんない仕事しか来ないんだろう、面白い仕事さえ来りゃ、俺だってこんなもんじゃないんだが、なんて嘆いているのはあまりみっともいいもんじゃない(笑)
『「お葬式」日記』
俳優だった伊丹氏が監督に転身したのも、そこに理由があったのだろう。
面白くなきゃ自分で面白くするべきだ。
『「お葬式」日記』
ライターのとるべき方法もあきらかだ。「面白くなきゃ自分で面白くする」。面白い仕事が来ないなら、自分で仕事を作ってしまえばいい。具体的には「みずからメディアを創る」などという手が考えられる。自分で自分に仕事を発注してしまうわけだ。最近の例でいえば、ブロガーやYouTuberが記事や動画を配信してマネタイズしているのは、まさに「自分で自分に仕事を発注」している図式になる。
とはいうものの、それがうまくいくとは限らない。博打的な要素も大きいからだ。成功は運次第という側面もある。「面白くする」ためにやっていることで「面白くなくなる」のは本末転倒だ。
必ずしも「みずからが発注者にまわる」ことが最適解にはならないことも頭に片隅に留めておきたい。
自分の能力を引き出して楽しむ
誰かから依頼を受けて仕事をするか、それとも自分が自分に発注するか。いずれにしても、「仕事を楽しむ」「仕事で遊ぶ」という精神こそが、ライター業を満喫することにつながる。伊丹氏の著者からはそんなことが学べる。
一例を挙げる。伊丹氏が監督した映画『マルサの女』に、脱税をしているパチンコ店の店長が登場する。その役を演じる伊東四朗氏の芝居を伊丹氏は絶賛する。
伊東氏の演技はきわめて水準高く、演出していてすこぶる気持ちが良い。自分の役をはっきり知っており、それを多彩なテクニックでうまく際立たせて楽しんでおり、しかもそれが技巧のための技巧におちいらず、また、かなり下品な人物を作りながら芝居が節度を失わず、卑しくならない。
『「マルサの女」日記』
伊東氏の仕事に対する姿勢は、ライターにもそのまま適用できよう。
その記事に求められる文章とはなにかを見極め、それを多彩なテクニックでうまく際立たせて楽しむ。しかもそれが技巧のための技巧に陥らず、読み手を楽しませる文章にして節度を失わず、卑しくならない。
プロフェッショナルの仕事というのは、歯を食いしばって取り組むものでない。大切なのは仕事を「楽しむ」ことなのだ。書き手が楽しいからこそ、テクニックが功を奏するのであり、読み手の心を刺激するわけだ。
俳優の仕事ではないが、こんな例もある。『マルサの女』にはラブホテルが重要な舞台として登場する。撮影は実際のホテルで行なわれているが、「各部屋は王朝風あり、アスレチック風あり、ディズニーランド風あり」と、伊丹監督は部屋の内装のつくりこみに感嘆の声を上げる。
デザインはこういうホテル専門の建築事務所がやっているらしいのだが、人知れぬ世界で大いに遊んでいる人たちがいるものだと感心する。デザインの水準というか完成度、乃至辻褄のあい方は非常に高い。映画の美術ではとてもこれだけのものは作れないだろう。
『「マルサの女」日記』
「人知れぬ世界で大いに遊」ぶ。これこそ私たちライターが目指すべき道なのだと思う。ライターたる自分自身にスポットが当たる必要はない。いや、むしろ当たっていけない。評価されるべきは、自分の仕事であって自分という存在ではない。
ひとくちに「ライター」といっても、あるべき姿はさまざまだから、これが唯一の正解とはいわない。だが、ひとつの究極の道であることもまたたしかだろう。
伊丹十三氏は、俳優であり監督であると同時に、優れたエッセイスト、つまりライターでもある。今回紹介した3冊の著書そのものが、ライティングのお手本、よいコンテンツづくりの見本になる点も最後に付け加えておきたい。






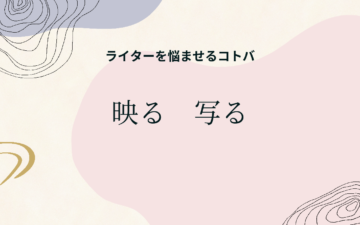
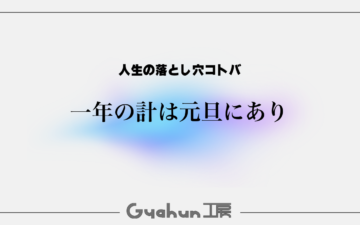




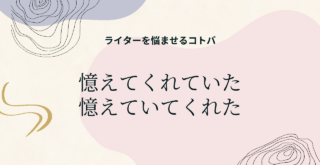
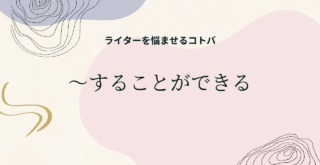
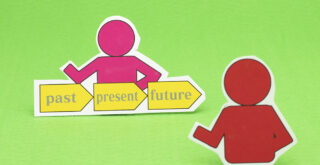
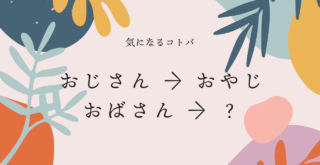


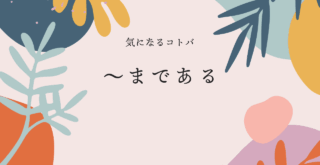

この記事へのコメントはありません。